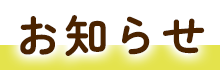あけましておめでとうございます、中村です。
新年恒例となりました【西暦素因数分解】ですが、今年はなんと2025=3^4×5^2、つまり45×45という素晴らしい年です。44×44=1936年、46×46=2116年ですから、相当長生きしていない限りは一生に一度の「平方数(自然数の二乗)の年」です。皆さん、共に祝い、幸せを噛み締めましょう。
ちなみに九九に出てくる数字をすべて足しても2025になりますし、1から9の3乗をすべて足しても2025になりますよ。すごい年です、2025年。
さて、堅苦しいおふざけもほどほどに本題。
冬期講習も終わり、受験勉強もラストスパートといったところ。唐突ですが、皆さんがこうやって勉強をしている一つの理由として、「新しい視点の獲得」があると私は思っています。
勉強して知識や考え方を蓄えていくことによって、今までよりも多くの視点から物事を見ることができたり、モノの見方の選択肢が広がったりするのです。
例えば、歴史や地理を勉強したあとに旅行をしたら、立ち寄った場所ごとに「ここは誰がいつ何をした場所なのか」を考えることができますね。お城であれば「どんな目的で建てられ」「どんなドラマがあり」「どのような結末を迎えたのか」などです。ちなみにこれは必ずしも知っている必要はなくて、そういった思考になれるかどうかが重要です。
しかし社会科目にあまり精通していない私のような人間は、どこに行っても「きれい!」「すごい!!」「かっこいい!!!」くらいの感想しか出せませんし、そもそもの背景知識がないから、行ってみたい場所すら思いつきません。だから旅行とかめちゃくちゃ苦手です。
(これは自分でもすごくもったいないな、と感じるんですよ。だから少しずつ知識を増やそうとしています。)
それで、冒頭で私が【西暦素因数分解】の話をしたじゃないですか。これって先ほど挙げた例と同じようなことだとも思うんですね。数学を勉強していると、数学の視点を身につけると、数字を見ただけで(正確には何かしらの操作を加えていますが)「面白い数だな〜!!」となるんですよ。
こうした日常の中でのふとした面白さに気付けることが、勉強をする意義の一つだと思います。皆さんも、学校での勉強と日常の気付きを結びつけて、新しい視点を獲得できるといいですね。私の授業なんかでは結構そういった話を余談として入れることもあるので、少し耳を傾けてもらえると嬉しいです。
以上、最近「迂回」の迂と「宇宙」の宇はつくりが同じ于であることに気付いてテンションが上がった男からのブログでした。ちなみに于は漢検1級配当の常用外漢字で、訓義は「まがる」や「大きい・遠い」だそう。意味が揃ってて嬉しいですね。
それでは。